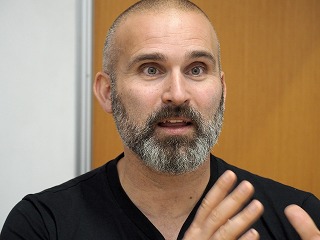©2018 TIFF
19世紀のデンマークの田舎。厳しい自然環境のなかで懸命に農業に勤しむイェンスは、過酷な冬を生きるために、心ならずも耐えがたい選択をする。家族のために裕福な農家と取引をしたことが、やがて彼のモラルと大切な存在をも犠牲にすることになる。デンマーク映画を牽引するマイケル・ノアーがリアリズムに徹して描くハードボイルドな男のドラマ。主演は『ヒトラーに屈しなかった国王』(16)のデンマークの名優イェスパー・クリステンセン。本作『氷の季節』は今年のコンペティションで、審査員特別賞と最優秀男優賞を受賞した。
――この作品が成立するまでの経緯をお話しください。
ルネ・エズラ(以下、エズラ):マイケルとは10年以上一緒に仕事をしています。最初が刑務所を題材にした“R”(10)、若者たちに焦点を絞った“Northwest”(13)があって、3作目が老人ホームをテーマにした“Key House Mirror”(15)と現代を描いた仕事をしてきて、次は過去に戻って歴史ものを挑むことになったのです。フィルムスクールを出たばかりの頃に知り合い、今やふたりとも父になった。その経験からこの映画を作りたかったのです。
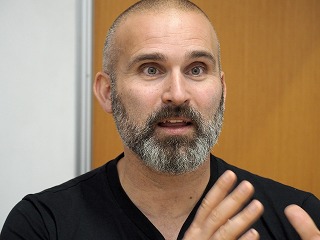
――それまで現在の題材であったのに、初めて歴史に目を向けたわけですか。
マイケル・ノアー監督(以下、ノアー監督):アメリカ映画のリメイク“Papillon”(17)を撮ったので、次は自分たちの歴史をリサーチしたいと思ったのです。歴史ものでオリジナルのストーリーで撮りたかった。実際に農民たちにリサーチをかけました。

――歴史を撮ることに興味を惹かれたのは分かりましたが、なぜ貧しい農家の話にしたのですか。
ノアー監督:私たちは、過去の時代を実際に生きた大半の人の姿を描きたくて、農民に行きつきました。今、僕は“飢え”は知りませんが、父親の責任、父親になる意味はよく分かってきました。
――監督が父親になったことが大きいというお話ですが、こういう父親にはなるまいという戒めですか。
ノアー監督:完成してみれば、確かに警鐘を鳴らしているように感じます。ただ、これは父に捧げた作品でもあります。代々受け継がれていく「ツリー・オブ・ライフ(人生の樹)」を象徴していると思います。歴史の流れのなかに我々はいることを忘れがちですから。
――監督は過去に戻ったけれども、描いたことは今に通じることなのですね。
ノアー監督:現在というものは、過去を通じて学ぶもの。温故知新というか、過去を振り返ることによって前に進めるものだと思います。今の僕の年齢になったからこそ、歴史に目を向けたと思います。自分の父親はもう亡くなっていますが、過去と現在を繋げるという作業が大事だと思うようになりました。
――しかもデンマークの名優イェスパー・クリステンセンが主演をしています。
ノアー監督:イェスパー・クリステンセンは、この映画そのものです。彼が体現した男らしさと脆さ、傷つきやすさ、そして彼の年齢こそが映画には重要なものでした。脚本はクリステンセンを想定した当て書きで、彼のために作った作品です。他には誰も考えませんでした。
――オリジナルのストーリーをどのように構築していきましたか。
ノアー監督:過去の保険証書をリサーチし、頻繁にあった政略結婚などを参考にストーリーを作っていきましたが、軸は父と娘の話に置きました。僕はクリント・イーストウッドの『許されざる者』(92)や、黒澤明の『七人の侍』(54)に倣ったダークな「西部劇」だと捉えています。
――自然光を生かした撮影が素晴らしいと思いました。
ノアー監督:自然光を使ったのは、現実的に見えるように意識した結果です。撮影のシュトゥルラ・ブラント・グロヴレンは、ベルリン国際映画祭銀熊賞に輝いた『ヴィクトリア』(15)などで知られる名匠ですが、撮るときには耳を使う。すべての音を聞きながら撮影します(笑)。
――マティルダ・アッペリンさんにはこれが、最初の長編ですね。
マティルダ・アッペリン(以下、アッペリン):以前から、マイケルの作品でアシスタントプロデューサーをしていたので大きな違いはありませんでしたが、責任がありました。そこがもっとも大きな違いです。
 エズラ
エズラ:上下関係を問わず、マティルダは意見は率直にいいます。だからこそ昇格したのです。彼女にとってボスは「映画」だけです。
――おふたりのお付き合いは映画学校からはじまったのですね。
エズラ:正直に言うと、フィルムスクールの頃はマイケルが嫌いでした(笑)。若いし、才能があるし、モテた(笑)。学校を出た10年後、刑務所の映画で一緒に仕事をしたら、非常にいいコラボレーションができました。だから20年来の知りあいですが、一緒に仕事をしてからは10年なのです。

――この作品で歴史にも触れたわけですが、今後、題材が変わることはあり得ますか。
ノアー監督:僕にはルールがひとつあって、常にひとつの視点から撮るということなのです。いろいろなジャンルを撮りたいという気持ちはありますので、ただこのルールは守っていくつもりです。
――監督を志したのはいつ頃ですか?
ノアー監督:クリエイティブな仕事をしている人がひとりもいないような小さな街に育ったので、監督になることを夢見ていただけですね。書くことが好きで、映像と合わせたいと思っていました。デンマークのヨーロピアンフィルムカレッジ(EFC)に通い、そこで出会った人たちと未だに仕事をしています。それが20年前の話です。
ノアー監督:EFCでドキュメンタリーを撮って、フィクションの見方も変わりました。フィクションにドキュメンタリー要素が入っているものが好きだし、ドキュメンタリーにフィクション要素が入っているのも好きです。両方の要素が入っているのが好きなのです。
――貧困、貧しさがこの映画の軸になります。今の世界に通じるものですね。
ノアー監督:貧困や飢えのニュースは、新聞などで読むと遠くの世界のように感じますが、映画に描かれると、気持ちを揺さぶられます。今の世界情勢においてはこの題材は強調すべきものだと思います。
エズラ:デンマークの歴史を描いていますが、ほんの少し前の時代のわけです。そこには飢えがあって、女性は投票権もなかった。この映画を通して、我々はどこまで進んできたかを再確認できます。
(取材/構成 稲田隆紀 日本映画ペンクラブ)